
15代S220型がクラウンの伝統を台無したとされ「ダサい」「売れない」「失敗」「しょぼい」の声を見かけました。その理由は「シックスライト」あるのか、迷走ぶりと失敗理由を解説します。
クラウンの概要
クラウン(CROWN)は、トヨタ自動車が1955年1月から製造・販売している高級乗用車です。
先代モデルは、15代目にあたり、S220型と呼ばれます。
キャッチフレーズは「CROWN BEYOND」。14代目クラウンのユーザー層は50~60代がメインでしたが、30~40代の輸入車を好む比較的若い層にもクラウンを訴求するため、「TNGA」に基づく「GA-Lプラットフォーム」を採用。シャシーをニュルブルクリンクで鍛え上げて「走る・曲がる・止まる」といった車両性能を大きく進化させて、スタイリングとともにスポーティなセダンとしての生まれ変わりが図られた。
15代目クラウンの記述になります。(wikipedia)
15代目シックスライトのデザイン採用が敗因
エクステリアデザインでは、ロングノーズの後輪駆動車らしいプロポーションと、クラウンでは初となるシックスライトウインドウの採用により、ルーフからテールエンドにかけての伸びやかで流麗なファストバック風のサイドシルエットを実現したとあります。
Wikipediaより引用ですが、これは、本当でしょうか。
アウディのような「シックスライト」が若返りになるのでしょうか?。全く根拠がありません。
日本におけるアウディとは、メルセデスとBMWの御三家ではなく、最近では、ボルボ人気に押された格下の車に成り下がりました。
なぜ、日本では人気が下降した、落ちぶれたアウディデザインのマネをする必要があったのでしょうか?。そもそもアウディはFFベースです。このあたり、ベンチマークとすべき車種の選定が先代から間違っていました。甚だ疑問です。
過去、ホンダ車の売れ線モデルの対抗馬として、ライバル車の人気モデルコンセプトを隅々まで研究し、ライバル市場のシェアを奪ってきたトヨタの最強マーケティングです。
マーケティングや営業部門が、FRクラウンとしてあるべき方向性を正しく分析していれば、こんなデザインにはならなかったでしょう。
よって、従来からのクラウンコンセプトを捨て、アウディを真似たコンセプトが最大の敗因です。
ゼロクラウンの12代目 S180型(2003年 – 2008年)で十分、若返りが図られています。日本の高年齢化やSUVや欧州車に流れる傾向は避けて通れません。これを否定するのは明らかに無意味だったのです。
アウディデザインが王道でなはい
少なくとも日本におけるアウディの販売台数は下降の一途です。アウディA4(B8型)のヒット後は低迷する一方であり、安価なグレードのA3/A2に販売の主力が移っている実態です。
セダンのベンチマーク車として見た場合、参考とすべきはメルセデスEクラスやBMW5シリーズであり、アウディはベンチマークの対象に全く相応しくありません。
日本オリジナルのミニバン「アルファード」が唯一無二の価値観「オラオラ」を開拓し、成長させた歴史を振り返れば、クラウンがベンチマークとすべきエッセンスは、先代クラウンの伝統と成功例アルファードのセダン化が日本の求めるセダンです。
日本の伝統的な王者クラウンのコンセプトを継承し、育てていくのがトヨタデザイナーの腕の見せ所だったのではないでしょうか。「過去の歴史を否定し、なぜかアウディを真似たコンセプト」が若返りの手法と理解した知識の狭さが失敗の原因です。
S220型クラウン・シックスライトの悲しい結末
- 車幅1800mm以内に収めるのは必須(日本的なコンセプト)
- 伸びやかなシックスライト・4ドアクーペデザイン(欧州車コンセプト)
この相反する二つ課題を両立させることが出来ず、デザイン的な破綻に繋がったのです。
 結果、やけに「細長いデザイン」と感じさせる大失敗デザインな車になってしまいました。
結果、やけに「細長いデザイン」と感じさせる大失敗デザインな車になってしまいました。
悲惨なデザインが生まれた背景
アウディは、同じセグメントであれば、メルセデス、BMWよりも車幅を広く、大きく見せようとするコンセプトです。ライバルを追い越せ理論がアウディの典型例です。
結果、アウディA6(Eセグメント)は、1885mmの車幅となり、シックスライトとの調和・バランスを考慮したデザインとして、熟成されているのです。
 トヨタデザイナーが、1900㎜に迫るアウディA6の実態を知らずに、シックスライトを車幅の狭い1800mmのクラウンデザインに無理やり押し込んだ結果、悲惨なS220型「超カッコ悪い細長いデザイン」が生まれたのが、背景になります。
トヨタデザイナーが、1900㎜に迫るアウディA6の実態を知らずに、シックスライトを車幅の狭い1800mmのクラウンデザインに無理やり押し込んだ結果、悲惨なS220型「超カッコ悪い細長いデザイン」が生まれたのが、背景になります。
(銀座のトヨタ重鎮御用達駐車場を考慮したという、本末転倒な理由も明らかになっています) アウディA6とクラウンの成り立ちや背景の違いが分かれば、ライバル車の実態や欧州事情すら理解しておらず、マーケティングを無視するような無謀なチャレンジは行わないでしょう。
アウディA6とクラウンの成り立ちや背景の違いが分かれば、ライバル車の実態や欧州事情すら理解しておらず、マーケティングを無視するような無謀なチャレンジは行わないでしょう。
シックスライトというコンセプトでは失敗だったと言えます。
欧州の4ドアクーペの実態を理解せず
欧州車では、4ドアセダンとは別に、4ドアクーペモデルを別車種として用意しています。
直近の不人気・大失敗モデルとして有名な最新レクサスLSもセダンから4ドアクーペにコンセプトを変更し、販売低迷しているのは記憶に新しいところでしょう。
メルセデスCLSもBMWグランクーペも専用4ドアクーペモデルであり、やや居住性を犠牲にしたモデルです。本線の王道セダン(Eクラスセダン、5シリーズセダン)は従来通り変わらず、4ドアクーペは別モデルの設定・ニッチマーケット用の実態も知らないのでしょうか。
クラウンは、4ドアクーペの流れに乗り、シックスライト化にした、とすれば本末転倒です。
レクサスLSがセダンからクーペ化した誤ちは、クラウンも一緒ですね。
- BMWの奇数グレードとして、本線のセダンを用意する
- BMWの偶数グレードとして、あくまでニッチマーケット用クーペを用意する。
- 欧州では4ドアクーペが流行っていると勘違いし、LSをクーペ化させてしまう。
クラウンの特徴は分厚いCピラー
クラウンの伝統的な特徴は、オラオラのグリルと、力強く太いCピラーに王冠マーク、横に幅広のテールランプに尽きます。
 この王道デザインこそが、トヨタが育ててきたクラウンそのものであり、日本の伝統的なセダンのベンチマークなのです。ヤンキー、オッサン世代から、免許返納年齢まで、年齢層に関係なく好まれる王道デザインです。これを継承していれば、何の問題も無かったのです。
この王道デザインこそが、トヨタが育ててきたクラウンそのものであり、日本の伝統的なセダンのベンチマークなのです。ヤンキー、オッサン世代から、免許返納年齢まで、年齢層に関係なく好まれる王道デザインです。これを継承していれば、何の問題も無かったのです。
過去を否定し、新コンセプトが正義なのか
他メーカーが、よくこのパターンで自滅していますね。
最近では、現行プリウスが大失敗デザインの黒歴史に名を遺したとも言えるでしょう。
アルファードなど、キープコンセプトの中で、正常進化しているトヨタ車とはえらい違いです。
15代目の販売不振、理由とは
全体的な価格アップが販売不振の理由なのか
10年前とは時代背景、安全装備も全く異なります。クラウンの価格アップがクラウン敬遠・不振の理由・原因ではありません。
同一価格帯のライバル車(欧州車)の装備内容がクラウンと同等以上になり、ライバル車に流れたというのが正解でしょう。むしろ、同一価格帯で格下の欧州車に劣る装備もあったのです。
価格設定でクラウンを敬遠する購入者はいないでしょう。
前期型のナビとエアコンの使い勝手が悪い
欧州車では10インチ超えが主流の時代に、7/8インチツインモニターやタッチパネルの操作性が抜群であるとする2015年以前の価値観で、2018年S220型モデルを登場させたことが失敗原因です。クラウンの想定ライバル車をあまりにも知らなさ過ぎました。これではクラウンが低迷するのは当たり前です。
フロントフェイスの形状
S210型とインパクトは変わりありません。前期と後期でフロントグリルやライト形状に大きな変化が無かったのは、前期モデルのフロントデザインは不評で無かったこと明示しています。現行プリウスやレクサスISの前期と後期を見れば、不人気デザインはコストがかかるパネルを入れ替えてでもデザインを大きく修正するのが実態なのです。
フロントマスクやリアテールのデザインを不人気理由に挙げる方もいますが、これは誤りです。
若返りコンセプトの失敗
従来のクラウンユーザーを切り捨て、若返りを図ったコンセプトの失敗です。クラウンという今まで育て上げたブランドの意味を理解せず、ユーザーの平均年齢が60から70代となった事実をダメだと安易に決めつけた結果、中途半端な「若返り失敗、整形失敗セダン」に変わってしまったということです。
すでに欧州車で目の肥えた30から40代から見て、全く魅力のないシックスライトや装備内容。
最近のトヨタ・もりぞうさんの指示なのか不明ですが「4代目プリウス前期」「5代目レクサスLS」など、斬新こそ正義、欧州車コンプレックスなデザインコンセプトで、先代よりも大きく販売台数減となっているのは、記憶に新しいところでしょう。
前期モデルのナビが小さくチープ
500万超えの車なのに、たった8インチナビ画面とか、あり得ません。2018年当時、欧州車Eセグメントで10/12インチが標準装備されていた時代に、あえてクラウンに搭載して来たのです。
 トヨタの最高級車ですから、8/9/10インチの妥協など有り得ず、レクサスのトップグレード同じ12.3インチナビ画面を標準化すべきだったのです。トヨタグループ内で、12.3インチを採用していたレクサスRX、ESやLSのコンセプトが活かされていないのが残念です。車格に見合ったナビ画面のサイズは、トヨタ車の頂点であるクラウンオーナーが一番気にする部分です。
トヨタの最高級車ですから、8/9/10インチの妥協など有り得ず、レクサスのトップグレード同じ12.3インチナビ画面を標準化すべきだったのです。トヨタグループ内で、12.3インチを採用していたレクサスRX、ESやLSのコンセプトが活かされていないのが残念です。車格に見合ったナビ画面のサイズは、トヨタ車の頂点であるクラウンオーナーが一番気にする部分です。
アウディのシックスライトという、意味不明なコンセプトを採用する前に、インテリアを重要視した12.3インチ画面を最初から採用するのがトヨタクラウンのあるべき姿です。
クラウンユーザーにとって「見栄こそ全て」であり、E/Dセグメント欧州車にナビ画面の大きさで劣ることなど絶対に許されません。
後期型では、12.3インチにアップし、ダッシュボードを全く違う形状に大きく作り変えて来ました。驚異の4インチアップです。前期オーナーが卵を投げつけたくなるレベルです。 この前期オーナーの怒りを鎮めるためには、2018年当時に、たった8/7インチの2画面構成でインテリアデザインへのゴーサインは正しかったのでしょうか。
この前期オーナーの怒りを鎮めるためには、2018年当時に、たった8/7インチの2画面構成でインテリアデザインへのゴーサインは正しかったのでしょうか。
トヨタ クラウン 新車販売台数推移
世代を重ねるごとに、販売台数は下降の一途です。セダン不人気などの理由もあるのでしょう。
15代目(S220型)クラウンに関しては、初年度、二年目以降も酷い低迷ぶりです。
2020年11月に後期型が登場し、不満の多かったナビ画面が大型化したものの、販売低迷の解決には繋がらなかったようです。16代目登場後の推移も記載します。
| 年 | 販売台数 |
|---|---|
| 2025年 | 56,717:エステート追加も前年比ダウン |
| 2024年 | 62,628:クラウンスポーツ・セダンの3車種体制でも、S210超え出来ず |
| 2023年 | 43,029:15代目S220を超えられない結果に終わる |
| 2022年 | 17,767:9月に16代目クラウンクロスオーバー発売 |
| 2021年 | 21,411 |
| 2020年 | 22,173:11月に後期型マイナーチェンジで、ナビ12.3インチへ |
| 2019年 | 36,125 |
| 2018年 | 50,324:15代目S220クラウン登場、たった8インチナビを搭載 |
| 2017年 | 29,085 |
| 2016年 | 39,813 |
| 2015年 | 44,316 |
| 2014年 | 49,166 |
| 2013年 | 82,701:14代目S210クラウン「グリル大型化、稲妻グリル」 |
| 2012年 | 29,963 |
| 2011年 | 29,927 |
| 2010年 | 40,529 |
| 2009年 | 40,216 |
| 2008年 | 74,904:13代目S200クラウン |
| 2007年 | 38,276 |
| 2006年 | 50,044 |
| 2005年 | 58,400 |
| 2004年 | 90,909:12代目クラウン「ゼロクラウン」 |
| 2003年 | 35,711 |
| 2002年 | 43,717 |
| 2001年 | 55,357 |
クラウン15代目S220型が失敗した理由とは:まとめ
たった「4年でモデル生命が途絶えた末路」その理由
- ターゲット層の若返りと内容のミスマッチが全て
- S210に比べて、70万の価格アップでライバルに流れた
- ロイヤルなどの本命グレードを無くした
- 不人気アウディを参考にしたミスマーケティングの開発陣
- チープなアンビエントライト
- チープなディスプレイサイズ
- クラウンのコスパ、存在価値、ライバルとの関係性を全く知らない、調べない開発陣
- ダウンサイジングターボ、直4でも全く問題ないがユーザーの理解不足を払拭できなかった
- 無駄なV6-3.5LやV8-5.0Lも残すべきだった
クラウンという伝統的なユーザーを切り捨て、新規ユーザー取り込みにも失敗した、ずさんな開発コンセプトは、失敗して当たり前の結果とも言える「まとめ」になります。


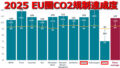
コメント