
スバルの黒歴史として、過去のものとなったスプレッドウィングスグリルです。
このグリルデザインは「ダサい」に認定され、販売不振になったのでしょうか。販売不振の理由は別にあると考えます。
スプレッドウィングスグリルとは
スプレッドウィングスグリルは、英語スペル「Spread-wings grill」です。
富士重工業(現・SUBARU)が採用していた自動車のフロントグリルデザインになります。
2003年から2010年までの販売モデルで採用していました。
スプレッドウィングスの英語訳
「スプレッドウィングス」 (英語:spread wings) は、直訳すると「広げた翼」の意味です。
背景
デザイナー:アンドレアス・ザパティナス
当時の富士重工業は竹中恭二社長のもと、2002年にスバル商品企画本部副本部長兼デザイン部長として初代レガシィのデザインを手がけた杉本清が担当。アドバンスト・デザイン担当のチーフデザイナーとして元・アルファロメオのアンドレアス・ザパティナスが、それぞれ起用されました。
- アンドレアス・ザパティナス氏の体制確率
- スプレッドウィングスのベースデザインは社内考案
- アンドレアス・ザパティナス氏のデザイン調整後にリリース
B11Sのコンセプトカー
2003年ジュネーヴ・モーターショーで発表された「スバルB11Sコンセプトカー」です。
フェアレディZ33風ライト、ブガッティ風グリルと思えば、それほど違和感はありません。

スプレッドウィングスグリルの装着車種
スバルR2(軽自動車)
2003年にR2に日本初登場したスプレッドウィングスグリルです。
個性的な軽自動車が多い中で、グリルデザインが足を引っ張っていたのでしょうか。
むしろ、グリルデザインよりもヘッドランプの形状(R2のライト下部の丸み形状)に問題があるように思います。丸目など可愛らしさを強調するライバル他社に対して、このライト形状が女性が好むデザインかと言えば疑問ですね。

スバルR1(軽自動車)
2005年登場の2ドアモデルです。特にグリルやライトのデザイン的な破綻は見られません。

スバルインプレッサ2代目
マイナー前の中期モデルに対して、マイナー後の後期モデルの完成度の高さです。
丸みのあるセンターグリルから、台形のスクエア風形状に変更され、全く違和感はありません。
後期ライト形状のカッコ良さは言うまでも無く、グリルはマイナスになるどころか、デザイン的にもインパクトのあるスタイリングに寄与しています。

スバルトライベッカ(輸出用SUV)
北米向けの大型SUVモデルです。
ライト下部の両端まで回り込んだデザインは、ポルシェカイエンを意識したとも言えます。センターグリルの突出量がボンネット先端を超えていなければ、スバルR1/R2同様に全く違和感ないデザインとも言えます。センターグリルが、かなり強調されており、好みが分かれるデザインです。
やや未成熟だった点は否めません。
 メーカーとしては、デザイン不評の「どこに問題があるのか」を掘り下げ、全体的なバランスから改良を施せば、全否定・全廃止という短絡的な結論にならなかったと思われます。
メーカーとしては、デザイン不評の「どこに問題があるのか」を掘り下げ、全体的なバランスから改良を施せば、全否定・全廃止という短絡的な結論にならなかったと思われます。
非常に残念に思います。
スプレッドウィングスグリルの成功例
スバルインプレッサ2代目最終モデル
ライト形状は「丸目、涙目、鷹目」と呼ばれ、2代目インプレッサは、大きなマイナーチェンジを実施しました。

前期「丸目」モデルは、散々叩かれて、中期「涙目」となりましたが、これも散々叩かれました。確かに「ダサイ」という意見や好みが分かれる部分も納得できます。
これらの意見をふまえて、後期モデルとしては「鷹目」となり、スプレッドウイングスのフロントグリルもスラントノーズになり、非常にカッコ良くまとまったデザインになっています。
ライト形状、フロントグリルとのバランスも非常に良く、スバル車としての存在感、ディテールのインパクトも十分にあります。
スプレッドウィングスグリルの完成形となり、成功例と言えるでしょう。
この後期モデルのデザインに対して異を唱える意見は非常に少ないです。
むしろ、最終型を完成系として評価し、継承させていれば、誰が見てもわかるスバルのデザインアイコンとなった可能性も高いです。
他メーカーの実態
レクサスの大型グリルが散々な言われ方をしていた時代もあり、デザイン的に未成熟な状態から、カッコ良いと感じる完成系へ次第に変化していったと思います。
スバルは、なせスプレッドウィングスグリルを止めたのか
実際に搭載したモデルが、販売台数不振であったというリアルな実態があったことも事実です。
メーカー本社に届いたデザインのクレームに耐えられなかったという話もありますが、デザイン的な改革に対する想定質問と対応策すらない戦略が敗因でしょう。
R1/R2の販売低迷はグリルが理由で無い
女性ユーザーが好まなかったというR1/R2の理由が、このグリルとするのは、やや微妙です。
R1は、軽の2ドアクーペという点で、超ニッチマーケットでした。
R2も、居住性を重視した軽トールワゴンが主流となる中で、居住性よりもデザイン、走行性能、安全性能、環境性能を重視したデザインが、そもそもニッチマーケットであったと思われます。これは、デザインが理由で無く、モデルコンセプトが失敗だったと言えます。
トライベッカはグリルが未成熟
北米向けのトライベッカについては、確かにグリルのインパクトが大きく販売不振に繋がった可能性が高いでしょう。
欧州メーカーのデザインコンセプト
メルセデス、BMW、アウディ、アルファロメオなど欧州メーカーでは、グリルを共通化しメーカーのデザインコンセプト、デザインアイコンを統一化する流れです。
ブランド力を高める効果もあるでしょう。
アルファロメオの逆パターン
一見、アルファロメオのセンターグリルの逆デザインと捉えれば、これはカッコ悪いところか、個性的なカッコ良さに繋がった可能性も高いでしょう
 好みが分かれるタレ目ライトの方が問題だったアルファ156です。グリル形状よりもライト形状の良し悪しが車デザインの要素として重要なことがわかる典型例です。
好みが分かれるタレ目ライトの方が問題だったアルファ156です。グリル形状よりもライト形状の良し悪しが車デザインの要素として重要なことがわかる典型例です。
デザインの熟成を待つべきだった
インプレッサ2代目の後期モデルを見れば、カッコ悪いところか、カッコ良さのインパクトに繋がっています。スバルの社内的に短期的に駄目出しの烙印を押したことは、失敗だった可能性も高いです。
ヘキサゴングリルの成功
スバル・インプレッサの4代目にて、ヘキサゴングリルとなり、レヴォーグで完成系となりました。
これは、世界的な販売台数的にも見ても成功したと言えます。
ただし、スバルブランドと言えば、ヘキサゴングリルをイメージすると呼べるまでのインパクトのあるデザインとは言えません。
スプレッドウィングスグリルはスバルらしさを表現出来ていなかった?
こんなネット意見もありました。本当でしょうか?
初代レヴォーグや兄弟車のインプレッサで、強烈にヘキサゴンなグリル形状をイメージしたことは無く、デザインアイコン、ブランドアイコンとしては、スプレッドウィングスの方が、よりインパクトがあり、記憶に残っているでしょう。
その点では、スプレッドウィングスグリルの方がスバル・ブランドをイメージする連想する個性的なデザインアイコンとして、インパクトに繋がったのではないでしょうか。
これこそ、スバルのブランディングというものではないでしょうか?
2022新型レヴォーグの失敗
ヘキサゴングリルを強調したデザインしたために、ライトが小さく離れ目になるデザイン的な失敗があります。カーオブザイヤー受賞にも関わらず、販売は低迷。これはグリルでなくライトがデザインとして重要な要素を占めていると言うことです。

まとめ
スバルインプレッサ2代目の最終モデルにおいて、デザイン的な違和感はなく、むしろスバルのブランドイメージを強調しつつ、カッコ良さが感じられるデザインです。
これは、自動車デザインとして、レクサスやBMWなど巨大化が進むグリルや縦長のデザインで個性を主張するアルファロメオのデザインに通じるブランディングを確立できた可能性もあるのです。
販売不振の理由は「スプレッドウィングスのグリル形状」が問題なのではなく、最重要デザインの多くを占めるライト形状を含む全体的なバランスがもたらすものと言えます。
「インプレッサ2代目の鷹目」は完成系デザインであり、高評価が圧倒的です。これをスプレッドウィングスグリルの失敗記事に含めるメディアに違和感があるでしょう。
ライトとグリルのバランスからの黄金比、ハロゲンからHID、LEDへとライト形状も変化していく中で、何がブサイク・ダサイのか、それは、過去の失敗例となる車を見れば、おのずと答えは出ているように思います。


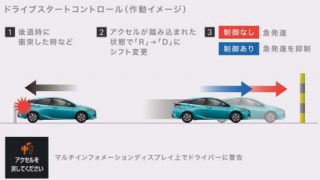




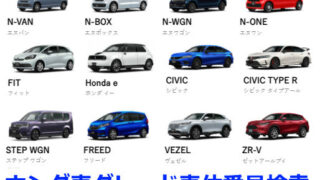








コメント