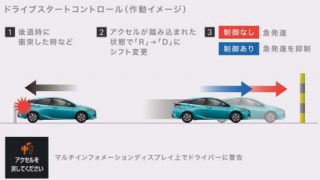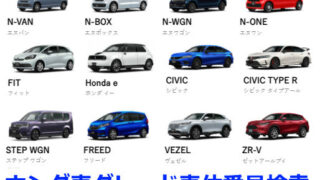自動車セグメント一覧と自動車セグメント分類や定義の具体的な内容を解説します。セダンやSUVセグメントの分類は車体サイズのみで分類・定義するのが妥当です。
自動車セグメント一覧
セグメント (自動車) – Wikipediaの解説は下記の通り。
ボディサイズの大型化やメーカーのコンセプト変更に伴い、グローバルインサイト社の分類に収まらない車が多数存在する。 現在では、マーケティングシステムズ社の分類による車体サイズ(全長)のみで分類を行う方法が有効である。 よって、ボディサイズの分類手法として、セグメント(ボディサイズ分類)で行い、ライバル関係や価格、ボディ形状、イメージを混同して考えないことが明快な手法である。

同一セグメント内にはセダン、クーペ、SUV、MPVなど、多様なボディ形状が混在します。ライバル関係やボディ形状を表すものでなく、ボディサイズ(全長)のみでセグメントを分類します。
セグメント規格発案の欧州における正式定義
欧州規格がベースであり、独自解釈は、全く無意味なことが理解できます。1999年の発案後、現在では概念が陳腐化しており、メディアの勝手な解釈や概念だけが独り歩きしている状況です。
現在では、用途に関わらずボディ全長サイズで分類し、セダンやSUVも同一セグメントとしてカテゴライズするのが明確かつ混乱の無い手法です。
- A:ミニカー
- B:小型車
- C:中型車
- D:大型車
- E:エグゼクティブカー
- F:高級車
- J:スポーツ用多目的車(オフロード車を含む)
- M:多目的車(ピックアップを含む)
- S:スポーツカー
時代と共にセグメントは変化する
VWゴルフを「Cセグメント」と言い切る評論家がいます。
もう、その例え話のレベルに驚きを隠せません。サイズを固定している車もあれば、時代と共に全長も全幅も大型化する車も多いことでしょう。大型化したシビックやアコードがその代表例です。
車名とセグメントを強引に紐付ける評論家による意味不明な分類は、時代の変化に適応できず、破綻しているのです。
全長サイズのセグメント表記なら、当時は、Bセグメントだった。現在は、Cセグメントに大型化している。ただ、その表現だけで済みます。
| 歴代ゴルフ | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) |
|---|---|---|---|
| I | 3275 | 1610 | 1410 |
| II | 3985 | 1665 | 1415 |
| III | 4020 | 1695~1710 | 1420~1435 |
| IV | 4155 | 1735 | 1455 |
| V | 4205 | 1760 | 1520 |
| VI | 4210 | 1790 | 1485 |
| VII | 4255 | 1790 | 1452 |
| VIII | 4295 | 1790 | 1455 |
マーケティングシステムズ社の分類が正攻法
セグメント一覧・セグメント分類表
グローバルインサイト社の分類方法(マーケット分類)は、定義が曖昧になり、時代の変化やモデルチェンジに全く対応出来ていません。
結果、誤りが多発し、評論家の語る記事では、全く適切でない酷い内容が散見されます。
そのため、マーケティングシステムズ社のセグメント分類方法(全長だけで分類)は、どの時代や変化にも適応できる最適な解釈・定義なのです。
ボディサイズは「Xセグメント相当」という使い方であれば、なんら問題ないでしょう。
| セグメント名 | 全長 |
|---|---|
| Aセグメント (Segment-Mini) | 3.7m以下 |
| Bセグメント (Segment-Small) | 3.71m~4.2m以下 |
| Cセグメント (Segment-Lower medium) | 4.21m~4.5m以下 |
| Dセグメント (Segment-medium) | 4.51m~4.8m以下 |
| Eセグメント (Segment-Upper medium) | 4.81m~5.0m以下 |
| Fセグメント (Segment-Luxury) | 5.01m超 |
自動車セグメント一覧を全長で分類するメリット
全長サイズの分類は、まさに単純明快です。価格やライバル関係を表すものでは、ありません。
セダンやSUV、MPV、スポーツカーを分類するものでも、メーカーのコンセプト変更に左右されません。トヨタやメルセデスのセグメント一覧として考えた場合、全長から分類すれば、車種やボディサイズの形状に関わらず、明確に分類できるのです。

Aセグメント(~3.7m)
トヨタ ライズ、ホンダ N-BOX、フォルクスワーゲン up!、フィアット 500

Bセグメント(3.71m~4.20m)
トヨタ ヤリス、日産マーチ、フォルクスワーゲン POLO、シトロエン C3

Cセグメント(4.21m~4.50m)
トヨタ カローラ、日産ノート、BMW 1シリーズ、メルセデス・ベンツ Aクラス

Dセグメント(4.51m~4.80m)
メルセデスベンツ Cクラス、BMW 3シリーズ

Eセグメント(4.81m~5.00m)
トヨタ クラウン、カムリ、BMW5シリーズ、メルセデス・ベンツ Eクラス

Fセグメント(5.01m~)
レクサス LS、メルセデス・ベンツ Sクラス、BMW 7シリーズ

SUVセグメント一覧
SUVのセグメント分類も全長でカテゴライズします。よって、明確な分類ができます。「Jセグメント」というオフロード車の分類方法もありますが、全く機能していないのが現状です。
| SUVセグメント名 | 全長 |
|---|---|
| AセグメントSUV | 3.7m以下 |
| BセグメントSUV | 3.71m~4.2m以下 |
| CセグメントSUV | 4.21m~4.5m以下 |
| DセグメントSUV | 4.51m~4.8m以下 |
| EセグメントSUV | 4.81m~5.0m以下 |
| FセグメントSUV | 5.01m超 |
日本における車セグメント
メディアが語る無意味なセグメント
時代の変化と共に価格もサイズも変化します。兄弟車の統廃合などにより、同一メーカー内のセグメントもライバル想定セグメント関係もあっと言う間、崩壊していきます。
| セグメント | 昔 | 現在 |
|---|---|---|
| Dセグメント | マークX、スカイライン、カムリ | |
| Eセグメント | クラウン、フーガ | カムリ、スカイライン |
| Fセグメント | クラウンマジェスタ、シーマ | クラウン、シーマ |
一見、昔のライバル関係を語るのに、都合が良さそうに見えますが、昔のセールスマンは「セグメント」などというワードは使いません。価格とサイズで真の競合車を列挙するだけです。
誤用と認識誤り
メルセデスのEクラスと「同じジャンルのセグメント」と言えば、イメージは出来るでしょうか。
ただ、マツダ・アテンザをメルセデスEクラスと比較検討するユーザーなどゼロでしょう。
セグメントなるものは、メーカーが仮想ライバル視し、勝手にカテゴライズした規格であり、全く意味が無いことが分ります。
同一サイズでも価格に大きな差があれば、購入の比較対象にはならず、セグメントという抽象的なカテゴライズになんの意味も無いことが理解出来るでしょう。
価格も異なれば排気量も異なりますし、モデルチェンジを行えばサイズやコンセプトは時代によっても変わって来ます。このようにヨーロッパを主体として出来たセグメントという名称は、日本に持ち込まれた馴染みの無い規格であり、ユーザーにとっては、全く意味が無い言葉なのです。
実際、日本車の販売現場では、お客に対して「セグメント」というキーワードは一切使いません。あくまで、競合車種の名前を直接挙げるだけでしょう。知ったかぶりの日本のジャーナリスト(評論家)が誤用していることが問題なのです。
写真はスカイラインですが、現行型は通称Eセグメントのサイズまで拡大しています。上級車フーガが消滅し、スカイラインがその代役なのです。
 北米では価格的にもメルセデスEクラス並みにライバル関係となっていますが、ユーザーに認知されているかは別問題です。
北米では価格的にもメルセデスEクラス並みにライバル関係となっていますが、ユーザーに認知されているかは別問題です。
グローバルインサイト社の分類方法が混迷の主原因
商品購入の分類方法としてのセグメント(segment)とは「何かを分割したもののうち、ひとつの部分」という定義があります。マーケティングの分野では、市場において共通のニーズを持っている顧客層の集団を指しています。
このセグメントは、車を分類するときにもよく使われており、欧州市場のマーケティング手法として活用されているようですが、日本では一般的ではありません。
グローバルインサイト社セグメントの定義の欠点
欧州のマーケティング手法として、ライバル車と競合する関係でグルーピングして表記する「自動車セグメント」なる定義が生まれました。たとえば、BMW3シリーズとメルセデスCクラスというライバル関係を1つのセグメントとしてグループ化する手法です。
一見、合理的な反面、価格やグレードによって上級モデルや下位モデルと逆転現象となってしまうケースが発生しています。フルモデルチェンジによる価格改定や大型化、コンセプトの変更などで、上位モデルとなっているケースも多いです。
特に、ホンダシビックなどは、過去の面影も無いほど大型しており、セグメントは適宜見直しが必要となるほど、曖昧な定義と言えます。
BMW2シリーズSUVとして、アクティブツアラー5人乗りとグランツアラー7人乗りでは、販売マーケティングとして同一セグメント化するのは無理があるでしょう。このようにBセグとかCセグとか、このような説明手法は全く意味不明と言えます。
グローバルインサイト社の分類と弊害
A~Fセグメントなる分類は、グローバルインサイト社による独自解釈の規格となります。
分類は、全長や価格、装備やイメージ(ここが諸悪の根源)といった抽象的な解釈による分類方法となっています。結果、市場は混乱を招き、舶来物好きの独自解釈に走ってしまったようです。
これを、知ったかぶりの評論家が誤用していることが、最大の原因なのです。
この分類の欠点・デメリット
同一車種でも様々なグレードや価格帯が存在するため、セグメントという分類が適切でないケースがあります。メーカー自ら、コンセプトを変更したケースでは、従来のセグメントイメージがマイナスになります。
地域で異なるセグメント定義一覧
下記の表も時間が経つにつれて、全く意味のないセグメント分類表になりつつあります。
全長4.9mとなり、国内ではレジェンドの代替としての役割を持たされたホンダアコードは、どのセグメントに属するのでしょうか?。5mを超えた5シリーズは、どのセグメントでしょうか。
| マーケットセグメント(北米) | マーケットセグメント(イギリス) | ユーロマーケット(欧州) | 車名 |
|---|---|---|---|
| マイクロカー | Microcar Bubble car | Aセグメント mini cars | Bond Bug/ Isetta/ Mega City/ Renault Twizy/ REVAi/G-Wiz |
| サブコンパクトカー | City car | – | Fiat 500/ Hyundai Eon/ Mitsubishi i-MiEV/ Peugeot 108/ Renault Twingo/ Smart Fortwo/ Toyota Aygo |
| エコノミーカー | Supermini | Bセグメント small cars | Ford Fiesta/ Kia Rio/ Opel Corsa/ Peugeot 208/ Renault Zoe/ Volkswagen Polo |
| コンパクトカー | Small family car | Cセグメント medium cars | Hyundai Elantra/ Honda Civic/ Mazda3/ Peugeot 308/ Renault M?gane/ Toyota Corolla |
| ミッドサイズカー | Large family car | Dセグメント large cars | Chevrolet Malibu/ Chrysler 200/ Ford Fusion/ Subaru Legacy/ Volkswagen Passat |
| エントリーレベル・ラグジャリーカー | Compact executive car | Acura ILX/ DS DS4/ Audi A4/ BMW 3 Series/ Mercedes-Benz C-Class/ Lincoln MKZ | |
| Executive car | Eセグメント executive cars | Chevrolet Impala/ Ford Taurus/ Hyundai Grandeur/ Holden Commodore/ Toyota Avalon | |
| ミッドサイズ・ラグジャリー | – | Cadillac CTS/ Chrysler 300/ Jaguar XF/ Acura TLX/ Volvo S80 | |
| フルサイズ・ラグジャリー | Luxury car | Fセグメント luxury cars | BMW 7 Series/ Lexus LS/ Mercedes-Benz S-Class/ Porsche Panamera/ Tesla Model S |
| グランド・ツアラー | Grand tourer | Sセグメント sports coup?s | Aston Martin DB9/ Bentley Continental GT/ Ferrari FF/ Jaguar XK/ Maserati GranTurismo |
| スーパーカー | Supercar | – | Bugatti Veyron/ LaFerrari/ Lamborghini Aventador/ Pagani Zonda |
| Convertible | Convertible | – | BMW 6 Series/ Chevrolet Camaro/ Mercedes CLK/ Volvo C70/ Volkswagen Eos |
| Roadster | Roadster | – | BMW Z4/ Lotus Elise/ Mazda MX-5/ Porsche Boxster/ Mercedes-Benz SLK |
| ? | Mini MPV | Mセグメント multi purpose cars | Citroen C3 Picasso/ Ford B-Max/ Opel Meriva/ Renault Kangoo/ Volkswagen Golf Sportsvan |
| MPV | Compact MPV | – | Chevrolet Orlando/ Ford C-Max/ Opel Zafira/ Renault Scenic/ Volkswagen Touran |
| Minivan | Large MPV | – | Chrysler Town and Country/ Kia Carnival/ Citro?n C4 Grand Picasso/ Renault Espace/ Toyota Sienna |
| Cargo van | Van | – | Chevrolet Express 1500 Cargo/ Fiat Ducato/Ram ProMaster/ Ford Transit/ Renault Master/ Volkswagen Transporter |
| Passenger van | Minibus | – | Chevrolet Express 1500 Passenger/ Ford E350 Wagon/ Mercedes-Benz Viano/ Volkswagen Multivan |
| Mini SUV | Mini 4×4 | Jセグメント sport utility cars (including off-road vehicles) | Daihatsu Terios/ Ford Ecosport/ Jeep Wrangler/ Peugeot 2008/ Suzuki Jimny |
| Compact SUV | Compact SUV | – | Chevrolet Equinox/ Ford Escape/ Honda CR-V/ Jeep Compass/ Kia Sportage |
| Mid-size SUV | Large 4×4 | – | Audi Q5/ Ford Edge/ Hyundai Santa Fe/ Jeep Cherokee/ Volkswagen Touareg |
| Full-size SUV | – | – | Cadillac Escalade/ Ford Explorer/ Range Rover/ Toyota Land Cruiser/ Volvo XC90 |
| Mini pickup truck | Pick-up | – | Chevrolet Montana/ Fiat Strada/ Renault Duster Oroch/ Volkswagen Saveiro |
| Mid-size pickup truck | – | – | Ford Ranger/ Chevrolet Colorado/ Mitsubishi Triton/L200/ Nissan Navara/ Toyota Hilux |
| Full-size pickup truck | – | – | Dodge Ram/ Ford F-150/ GMC Sierra/ Nissan Titan/ Toyota Tundra |
| Heavy Duty pickup truck | – | – | Chevrolet Silverado HD/ Ram Heavy Duty/ Ford Super Duty |
| Special purpose vehicle | – | – | Lincoln MKT Livery |
一般的なセグメント分類
マーケティングの分野では、市場における共通した購買要求を持つグルーピングを指します。製品のカテゴリが似ており、製品の価格や使い方など、色々な項目で購入要求や購買行動が共通しているグループです。グループ分類は下記の3パターンです。
1.セグメンテーション(Segmentation)
調査項目を多様な角度からグルーピング(セグメント化)を実施し、顧客のニーズごとにカテゴライズ。
2. ターゲティング(Targeting)
分類された複数のグルーピングをベースに最も競争が優位性となるグループを選定し、グループに追加します。
3. ポジショニング(Positioning)
選定グループの顧客層に対する優先順位を深堀することにより、顧客のニーズにおけるシェアや順位を見つけます。
セグメントの分類手法
一般的なセグメントの分類手法
- ニーズ
- 購買行動
- 地理的変数
- 人口動態変数
- 心理的変数
- 行動変数
- 製品の使用パターン
上記のセグメント化(セグメンテーション)」と呼びますが、グローバルインサイト社の分類のような分類手法は、分類者によって価値観が分かれます。
日本では意味の無いセグメント定義
もはや自動車ジャーナリストも意味不明なキーワードであることに気付いているのでしょう。代表的なBMW3シリーズやメルセデスCクラスなど、誰が見ても混同しない車種でしか使わないようになっています。
- 価格帯のカテゴリー
- ボディサイズのカテゴリー
- セダンのカテゴリー
- スポーツカーのカテゴリー
- SUVのカテゴリー
誰もが明確な購入意思とライバル関係であることを認識できるカテゴリー分けが良いです。欧州で生まれた当初のセグメントとしての意味は、メーカーのコンセプトの変化により、変動するため意味が無いのです。
自動車セグメント分類のまとめ
日本では自動車セグメントという言葉は一般的ではなく、ジャーナリストの誤用が全てです。
よって、このような意味不明なキーワードの意味すら理解せずに多用するジャーナリストは信用すべきではありません。
得意になって「セグメント」というキーワードを使っている方がいたら教えてあげましょう。
車体の全長のみでセグメントを分類・定義することが合理的なのです。
セグメントというキーワードを使わず、具体的なライバル車を羅列して比較説明している記事を信用すべきなのです。