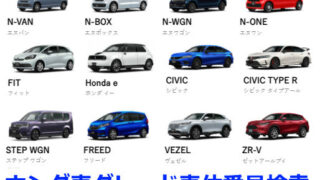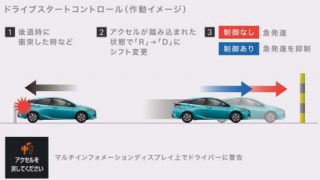最新のトヨタ・デュアルブーストハイブリッドステムは、いまどき6ATを採用しています。時代に逆行する6ATとトルコンレスATのデメリットを独自の分析と洞察で解説します。
デュアルブーストハイブリッドステムの概要
従来のTHS2とは
トヨタ製ハイブリッドシステムとしておなじみの「TOYOTA HYBRID SYSTEM II」(THS2)です。
世界初の量産ハイブリッドとして、プリウスに搭載されたTHSは、駆動・回生用のモーターと、発電用のモーター、それにエンジンからの駆動力を遊星歯車(プラネタリギヤ)でコントロールするシステムです。
プラネタリギヤ特有のスムーズな駆動力切り替えで、2モーターを使ったシリーズパラレルハイブリッドは、第5世代となり、コンパクトで高効率な性能に磨きがかかっています。
トルコンとトルコンレスの違い
トルコンAT
エンジンとミッションは、トルクコンバーター(流体クラッチ)が用いられます。この流体により、駆動系の衝撃と摩擦を吸収し、スムーズな変速を行います。
近年では、DCTやMTの変速スピード・効率のメリットを凌駕したトルコンATが登場し、スポーツモデルですら、トルコンATを採用する時代になっています。
トルコンレスAT
トルクコンバーターの代りに、湿式多板(機械式クラッチ)を用います。流体を用いないため、ダイレクトなシフト感が得られますが、それはユーザーが望む高級感とは程遠いものです。
大きなシフトショック、クラッチ寿命などを考えれば、渋滞が多いアジア・北米圏に不向きなシステムです。VWやホンダのDSGでリコールが多発したことは記憶に新しく、機能的に高負荷が避られません。トラブル多発に繋がる構造的な仕組みは、過去の歴史から学習済のはずです。
今回のDBHSとは
DBHS(デュアルブーストハイブリッドシステム)の仕組みは、下記の通りです。
- エンジンからの出力をダイレクトにモーターに導き、モーターとエンジンの力で前輪を駆動する新開発の1モーターパラレルハイブリッドシステム
- トルコンレスの6AT
- 後輪を駆動するインバータ一体形のeAxle(イーアクセル)
前輪と後輪の二つのシステムを組み合わせたハイブリッドシステムになる。